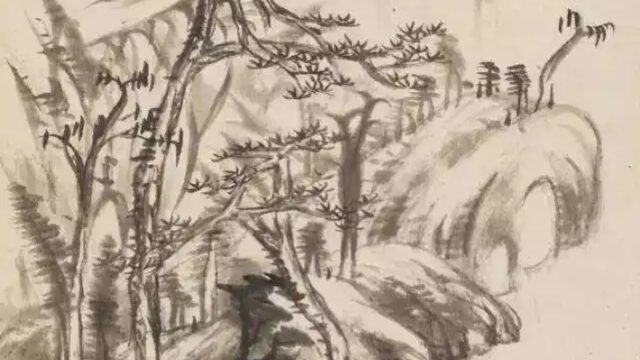「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、明代末期~清代初期くらいの詩についてみていきます。
明代末期は、だいたい天啓帝(1620~27年)、崇禎帝(1627~44年)あたりです。清代初期は、なんとなくですが1644~1680年代(順治帝~康熙帝の初め)あたりになります。
この時代の詩って、なんていうか、そこはかとなく落ちつかないというか、そこはかとなく淋しげなのです。わたしは、中国の磁器をみるのも好きなのですが、このころの詩って、ちょっと疲れて潰れてしまっている感がなんとなく磁器に似ています……。

こちらが明代末期の磁器なのですが、明末清初の詩もこんなふうにちょっとへにゃへにゃとくたびれている感があります……。というわけで、さっそく紹介に入っていきます。
明末
まずは、明代末期です。
明は、たびたび北方の遊牧民&南の海賊に苦しめられて、しだいに弱っていき、豊臣秀吉の朝鮮侵略を追いかえしたりして、いよいよ疲弊していきます……。1600年代に入ると、しだいに「もうどうにもならん」感が漂ってきて、万事が雑然としてバタバタして疲れていきます……。
ひんやりとした谷に木の葉がそよぐ秋に、ぐったりと疲れて白菜を取りにいくのもめんどくさく、隣りの人がごろごろと大きな芋をたくさん貯めているようだったので、分けてもらって炙って食べました。
寒谷涼生萬葉風、病来懶去採青菘。丈人甕底如拳芋、乞與山厨煨火紅。(沈中柱「與鄰丈乞芋」)
……疲れきっています(泣)
このぐったりと力の無い感じが、いかにも明代末期的です。ばたばたと小さく動いているけど、根っこにはどうにもならん感があふれていて、その場しのぎが重なって、いよいよ疲れていきます……。
さらさらと良い香りのする木々を束ねた舟にて、あなたを送れば水がさらさら流れました。どこかで鳴っていた笙が止まると花が薄く雨にぬれていて、わずかな衣と細い高髷は秋の木の葉につつまれていきました。
桂棹蘭橈束両頭、送君愁共水争流。参差吹罷芙蓉雨、雲鬢羅衣不耐秋。(陸時雍「沈恤部子先讀予騷疏慨然有咏見贈於其行也賦此酬之」)
ほっそりとして途絶えそうなのに、なんとか残っている感がすごくそれっぽいです。明末の詩って、弱々しくも続いている感があるというか、わずかに細くて温かい――みたいなイメージです。
つぎは少し長めのものを行ってみます。
四十もある蘭江の瀬のうち、石塘はもっとも恐ろしい難所で――、さらさらと白い絹を敷きつめたごとき堤のそばには、ぐるぐるとした流れが岸を斬るごとく馳せていて、長い雲がどこまでも漂うごとく、するどい崖の下をごろごろと駆けていく。
蒼く黒い水は龍蛇さえも凍えさせるほど深くして、疲れてひっくり返りて路に打ちあげられるかと思うほどで――、また大鯨のがぶがぶと暴れて、口を尖らせて川底にて遊ぶごとくして、流れは乱れて巌の罅(ひび)に差しこみ、ぎりぎりとして割くような声をさせて、甕を砕いてごろごろとして、大鐘を噛み割りて白い牙をむく。
亀なども避けるほどの荒いところにて、小舟などは近寄らず、百丈ばかりの流れにて千人があつまっても、わずかに進んで流されるばかりで、こんなふうに疲れ果てながら一日が過ぎて、あの灔澦の水もこんなふうだったのかもしれない……。
四十蘭江灘、石塘最奇忤。匹練偃重隄、灝流截奔鶩。長雲奔陂陀、断岸沈轗軻。恍疑潜虬寒、暴甲横江路。又如渇長鯨、厲吻馮川過。乱流攻衆罅、拗鬱声噴怒。剖甕鞳噌吰、蠡鏞呈噛蠧。黿鼉未敢遊、舴艋詎能渡。百丈集千夫、尺寸費朝暮。伶仃古所歎、灔澦従兹賦。(徐遠「石塘浜」)
全然ちがうものを詠んでいるはずなのに、どことなく漂ってしまう「どうにもならない感」がすごく独特です……(まぁ、わたしがそういうものを選んでいると云われればそうなのですが)
あと、「灔澦の水」は、むかしの四川省にあった水の難所です。水の描写がすさまじいというか、黒々としていて「甕を砕いてごろごろとして、大鐘を噛み割りて白い牙をむく(剖甕鞳噌吰、蠡鏞呈噛蠧)」が、まるで襲ってくる何かみたいです。
もうひとつ、水を描いたものをのせてみます。
巌はぐねぐねと曲がっていて、水はがたがたと折れていき、千尺ほどのところをざッと落ちて、わずかに巻くようにして岩の凹みに入っていく。白い筋はどぼどぼとくずれて、古い鉢に秋でも雪を盛ったような――。
雲がその間を流れては、ついでに水に捕まって落ちていき、そんな冷たい光は目を刺すようで、でもどこかぼんやり煙ったままなのでした。だらだらと流れてしだいにゆるくなって、枯れ蓮が幾本も立っているところがあって、龍がいないときは水は冷たく、龍が居るときは水は生温いと云いますが、その龍は風まかせに飛んでいるらしく、水の上の葉がぼそぼそと隅に溜まっておりました。
巌形既以紆、泉勢因之折。直下千尺峰、洄漩注空穴。白練化為環、古鉢盛秋雪。雲過偶然堕、長與高空絶。冷光撲鬚眉、照影終不澈。蜿蜒誰所蓄、藕孔新絲結。龍去潭水寒、龍来潭水熱。去来恒随風、掃此潭上葉。(夏緇「大小龍潭」)
絶妙にたるんでいます……。ふつうは「古い鉢に秋の雪でも盛ったような(古鉢盛秋雪)」みたいな句のあとに「その龍は風まかせに飛んでいて、水の上には葉がぼそぼそと溜まっておりました(去来恒随風、掃此潭上葉)」みたいなちょっと汚げな句って、入れなくないですか……。
あと、風任せに飛んでいる龍って、全然力を感じないのですが、どこかぼんやり惚けてしまっているのが、すごく明末っぽいです。龍がたまに戻ってきて、枯葉に埋もれそうになっている水をなんとか開けさせて潜っていく――みたいな「その場しのぎ感」も明末です……。
清初
というわけで、ここからは清代初期をみていきます(もっとも、明末清初って、あまり離れていないのですが、清初っぽい作風ってあるんですよね)
山の雲はぼやぼやと白くして、山なのか水なのかもわからぬほどで、濤の声は天の風のようにもみえて、まわりはどこまでも雲ばかりなのでした。
渓雲淼淼白、不辨山與水。濤声疑天風、身在雲霄裏。(胡明遠「屯渓」)
清代初期って、すごく冷たいんですよね……。明末がわずかに残った生温さの中でぼそぼそと続いていく感じだとしたら、清初ってもはや割れてしまって壊れた後みたいなイメージがあります。
ちなみに云っておくと、清はもともと東北部(遼寧・吉林・黒龍江の三省あたり)から入ってきたので、清代初期はどちらかというと新しい王朝というより、吹きっさらしの転覆期みたいな雰囲気が近いかもです。
ここでも、「周りはすべて雲ばかり(身在雲霄裏)」みたいな句が、どこに行くのか分からなくて、しかも「濤の声は天の風のようで(濤声疑天風)」もすごく吹きさらしの冷たさにあふれていませんか……。
古い洞はわずかばかりの部屋があって、雲が閉ざして幾年も経ち、桃の花が咲いたころも神仙は去ったままで、古い石段も苔だらけなのでした――。
古洞如斗室、雲深鏁不開。桃花亦仙去、遶径尽蒼苔。(胡明遠「桃花洞次縉雲李若矦韻」)
こちらも同じ人の作品なのですが、明末が「風任せにたまに戻ってくる龍」だとしたら、清初は「神仙も去って久しい洞」みたいな感じです。
明末って、細々と何とかつづいていてバタバタと少しだけもがいているようで、清初って壊れてしまったあとの静かな冷たさが漂っているという違いがあるような……(あと、明末って薄くて鈍いピンク、清初って白っぽい蒼がイメージカラーかもです)
江水の春の光は楼をつつむようで、飾り廊の霞はどこまでもつづいているのですが、呉越は欄の外にうねうねと広がっていて、江はあちこちに分かれつつ街をめぐって溜まっておりました。霞は遠くの木々をつつんでぼやけ、浪はどこからか涌いてあふれるように満ちてくるのですが、わずかに風が来て北のほうをみれば、ぼやける雲の先に蓬莱でもあるのかもですが。
東南佳気鬱楼台、画棟霞連睥睨開。呉越星分従檻出、江湖水合抱城廻。烟含萬樹天辺尽、浪湧三山海外来。此際臨風瞻北極、五雲深処是蓬莱。(袁袾「題海昌北城楼」)
これはちょっと複雑な詩です。まず、いつでも「ぼやける雲」があふれるように漂っていて、この世から切り離されている感がすごいです……。
あと、「ぼやける雲の先にある蓬莱(五雲深処是蓬莱)」がすごく好きです。蓬莱(仙境)はどこかにありそうなのに、ただあちこちにぐちゃぐちゃと畳まれたような山や江が溜まっていて、もはやぼやぼやと全てがぼやけていて、すごく不思議です……。
なんていうか、清初の詩って、風景を書いているのに、風景をみていないというか、風景がぐちゃぐちゃぼやぼやと潰れている感だけが出ているんですよね……。この「世界が澱み溜まってどろどろぼやけて沈んでいく感」が清初っぽいです。
というわけで、かなり私の思っていることばかりを語る記事になってしまいましたが、明末清初の詩について少しでも魅力が伝わっていたら嬉しいです(ちなみに、今回は超マイナーな隠れた名品ばかりを選んでみました♪)
お読みいただきありがとうございました。