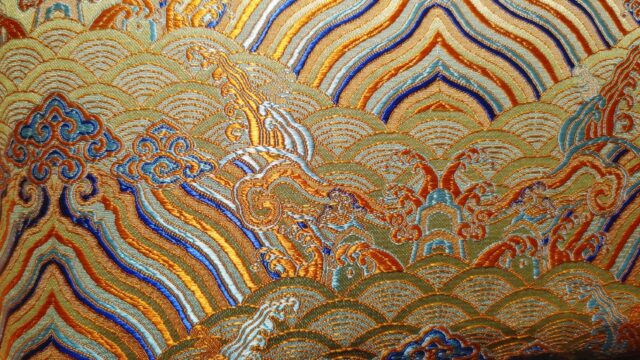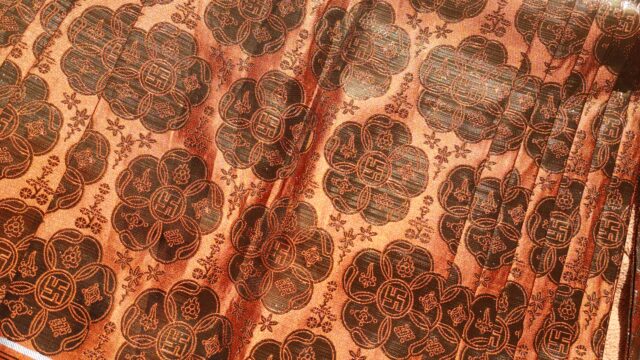「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
どうでもいいですけど、古代文学(中国の楚辞とか、日本の万葉集とか)って、すごく読みづらいと思いませんか……。
わたしは、はっきり云って、万葉集の和歌をみたときに、そもそもどこに感動すればいいのか分からない……という気分だったんですよね(笑)というわけで、今回は古代文学のわかりづらい魅力についてです。
あと、古代文学については、よく「古代の文学は呪術的なor祭祀的な……」みたいな話があったりするけど、それも私は全然分からなかった側なので、すごく大まかですがまとめてみたいと思います。
ちなみに、ここでいう「古代文学」は、日本では飛鳥~奈良時代、中国では先秦~後漢くらいです。
呪術時代
まず、古代文学の中でも、もっとも古いものを「呪術時代」みたいに呼んでおきます(この時代区分は、すべて私がつくった用語です……)
この頃は、とにかく自然は怪しく恐ろしい霊的な力があって、不気味な神々がすんでいて、呪物などもあって……みたいに、そういう妖しいものが本当に効くと信じられていた時代です。
みもろの 神なび山ゆ との曇り 雨は降り来ぬ 天霧らひ 風さへ吹きぬ 大口の 真神の原ゆ 思ひつつ 帰りにし人 家に至りきや(万葉集3268)
「みもろの」は神の宿ること、「神(かむ)なび山」は神のこもる山です。「大口の」は大きな口で、「真神(まかみ)」は狼のことです(ふたつ合わせて「大きい口の狼」)
神のやどる山からもやもやと不気味な雲があふれてきて、狼すらいるようなところを抜けて、あの人は無事に帰られたのだろうか――みたいな自然の不気味さが漂うような作品です。
この自然の不気味な霊などが涌いている感じって、現代人の私にはまったく理解不能でした……(自然の霊を恐れるような感性で、風景とかをみていないのかもです)
あるいは翳りてあるいは明るくして、ひとびとは司命神の為すことを知らず――。老いはしだいに迫りて枯れていき、司命の神はどこに行かれるのか――。龍に乗りてさらさらと馳けて、高く飛びて天を行き、桂の枝をふって呼んでもふり向かず、わたしは老いながら悲しむだけで……
一陰兮一陽、衆莫知兮余所為。……老冉冉兮既極、不寖近兮愈疏。乗龍兮轔轔、高駝兮沖天。結桂枝兮延竚、羌愈思兮愁人。(九歌・大司命)
こちらは中国の例なのですが、ひとびとの寿命を司る「大司命」という神と、しだいに老いていく中で大司命にふり向いてもらえない人の悲しみ――みたいになっています。
この感覚も、本気で大司命がいると思ってないと出てこないというか、そういう呪術的なことが効くと思っている世界じゃないですか……。もうひとつ、神々を祀ることが本当に効くと思っているような作品をのせてみます。
礼を終えて鼓にあわせて、花を持ってひらひらと舞えば、巫女は歌いてゆらゆら流れて、春の蘭と秋の菊――。いつまでもこの祭りは絶えず。
成礼兮会鼓、伝芭兮代舞、姱女倡兮容與。春蘭兮秋菊、長無絶兮終古。(九歌・礼魂)
これも神々を祀って、いつまでもその神々に守られて……みたいな感覚が、すごく現代人からすると独特です……。
こんなふうに、呪術時代の作品って、神々を祀ったり、呪術的なことをすると本当に効くと思っている感があって、生きることと神々や自然の霊が深く絡んでいます(感情だけで祀っているのではないというか)
あと、呪術時代の自然って、すごくどろどろしている暗さがあります。
隠(こも)りくの 泊瀬小国(はつせおぐに)に 妻しあれば 石は踏めども なほし来にけり(万葉集3311)
「隠(こも)りく」は奥まっているところ、「泊瀬(はつせ)」は奈良県の長谷寺あたりです。そんな奥まって暗いところに、妻がいるので石を踏みながら会いにきました――みたいに、すごく風景が暗くて恐ろしいというか、不気味なのです……。

国家祭祀時代
というわけで、さっきの呪術時代は、どちらかというと小さい身の周りの世界でしたが、しだいに王朝の安寧を祈るための祭りみたいになっていくと、少し様子が変わります。
榊葉の 香をかぐはしみ 覓(と)め来れば 八十氏人(やそうじびと)ぞ 団居(まとい)せりける 団居(まとい)せりける
瑞籬(みずがき)の 神の御代(みよ)より 篠(ささ)の葉を 手(た)ぶさに取りて 遊びけらしも
こちらの二つは、平安初期の宮中の神楽歌なのですが、自然の霊力の恐ろしさというより、神々に守られている王朝の安らかさを感じさせます。
もっとも、二つめのほうは、かなり「巫女は歌いてゆらゆら流れて、いつまでもこの祭りは絶えず(姱女倡兮容與、……長無絶兮終古)」にもかなり似ているので、呪術時代と国家祭祀時代の中間でしょうか……。ちなみに、「瑞籬(みずがき)」はいつまでも瑞々しい籬(かきね)です。
なので、呪術時代の不気味で恐ろしい神々は、しだいに安定して王朝を守ってくれる神々になっていき、風景も王朝の繁栄を飾るようになっていきます。
やすみしし 我ご大君の 常宮と 仕へ奉れる 雑賀野ゆ そがひに見ゆる 沖つ島 清き渚に 風吹けば 白波騒ぎ 潮干れば 玉藻刈りつつ 神代より しかぞ貴き 玉津島山(万葉集917)
こちらは山部赤人の長歌ですが、「やすみしし」は「安らかにみているor八隅まで知っている」、「そがひ」は背後です。
雑賀野(和歌山県)にある離宮から、海のほうをながめてみれば、清らかな渚には風がふいて、白波が美しく、潮が引けば豊かな玉藻がたくさん茂っているようなうつくしい島があって――みたいな感じで、きらびやかな自然につつまれた王朝の美しさを喜ぶような作品です。
この「王朝と一つになったような感性」って、これも呪術時代の不気味さと並んで、現代人には分かりづらい感覚なんですよね……。
ちなみに、柿本人麻呂の有名な「近江の海夕波千鳥汝が鳴けば……(万葉集266)」も、薄く暮れていく近江の海をみていると、昔の近江の宮室が、いまは荒れてしまったのが悲しく思われる――みたいな、王朝とひとつになったような感情です(私は初め全然分からなかったです)
あと、よく「万葉集は、雄渾でおおらかで力強い作風」と云われるけど、たぶん荒々しくて激しいというより、ゆったりと大きな王朝と一つになっているようなどっぷり感が、雄渾(雄大でどっぷりと溶けている)みたいな印象になっているのかもです。
(余談だけど、神楽歌は呪術+国家祭祀Mix、人麻呂・赤人は国家祭祀時代……みたいに、必ずしも時代順ではないことが多いです。民間寄りでは古い呪術色が残っていたりします)
こういう作風は、中国では後漢あたりに多いです。
きらびやかなる漢の世にて、穏やかにして輝かしく、世ごとにその徳を重ねれば、ただ泰山での祭りのみが久しく行われていないのが惜しまれるばかりで、その祭りは神人も喜び、海内の祝うものになるでしょう――。
そんなわけで、車馬を整えて、輿に乗りて天霊の険しき路を上り、雲気をまとう太乙神のごとき車を引いて入れば、天は清らかな雷を涌かせて、とろとろりらりらと厳かなのでした。
盛乎大漢、既重雍而襲熙、世増其德。唯斯岳礼、久而不修。此神人之所慶幸、海内之所想思。……乃命太僕、……乗輿登天霊之威路、駕太一之象車、……天動雷震、隠隠轔轔。(後漢・崔駰「東巡頌」)
この「王朝の儀礼の美しさはみずからの喜び」みたいな感覚って、すごく独特というか不思議です。「天は清らかな雷を涌かせて、とろとろりらりらと厳か(天動雷震、隠隠轔轔)」みたいな、王朝を支えるごとき雷雲……って、呪術時代の不気味さとはかなり違っています。
(どうでもいいけど、私は後漢の作品をみてから、やっと柿本人麻呂・山部赤人あたりの魅力がわかってきたタイプでした……。後漢の作品って、乾いているようにみえて不思議な味があります)

抒情時代
ということで、ようやく抒情時代ですが、実は呪術時代から抒情に入りつつあるor国家祭祀的なものから一人の抒情に入りつつある……みたいなものがかなり多かったりします。
恋せじと御手洗川(みたらしがわ)にせし禊(みそぎ) 神はうけずぞなりにけらしも(古今集501)
こちらは呪術時代と抒情時代の間みたいな感じです(さっきの神楽歌と同じく平安初期です)
「御手洗川(みたらしがわ)」は、神社の近くのお浄めの川ですが、そこで身を洗ったはずなのに、神さまの力はなぜか効かなくて……みたいなところが、呪術からはみ出しつつある抒情っぽくないですか……。
つづいては、国家祭祀時代&抒情時代の混ざってそうな作品をみていきます。
河間太守の張君は、その姿はひっそりと澄んで深く、道德は流れあふれて、文章は雲の如くきらめき、その話は玉を散らして練りあげたようで、人の窺えぬような技に通じて、きらきらひらひらと明らかで、神と通じるようにすら思われた。
地元の薦めで官になり、天文のことを司る役になってのちは、暦のことにも深く通じて、いよいよ漢の王朝を照らすほどで、河間郡の太守となってのちは、礼を重んじて治め、民もとても喜んだのだが、その命運は永からずして、ぼんやりと暗い闇に襲われてしまい、天は世を亡ぼすのか、世はあの伎芸文化を奪うのかと嘆かれるほどで……
河間相張君、……天姿濬哲、……道德漫流、文章雲浮、……瑰辞麗説、奇技偉芸、磊落煥炳、與神合契。……初挙孝廉、……遷太史令、実掌重黎歴紀之度、……光照有漢。……遂相河間、政以礼成、民是用思。遭命不永、暗忽遷徂。……天泯斯道、世喪斯文。(後漢・崔瑗「河間相張平子碑」)
まず、「その話は玉を散らして練りあげたようで、人の窺えぬような技に通じて、いよいよ漢の王朝を照らすほど(瑰辞麗説、奇技偉芸、……光照有漢)」が、すごく王朝を支え飾るような風景に似ていませんか……。
あと、「天は世を亡ぼすのか、世はあの伎芸文化を奪うのかと嘆かれる(天泯斯道、世喪斯文)」が、わずかに“王朝とひとつになり切れない感”みたいなものを想わせて、国家祭祀の中にもわずかに抒情が混ざってしまっているというか……。
ちなみに、日本では平安初期、中国では後漢末あたりに抒情色の多いものがでてきます(もっとも、中国は国家祭祀&抒情Mixがずっとそれなりに残ってます)
というわけで、かなりぐちゃぐちゃと複雑な流れになっていますが、自然の霊力などを本当に怖れるように信じていた時代から、しだいにそれが国家祭祀にまとめられていって、不気味さは消えていって、しかもその二つに収まりきらないものがしだいに抒情として育っていく――みたいな流れが、ちょっとでもイメージできていたら嬉しいです。
けっこう長い話になりましたが、お読みいただきありがとうございました。