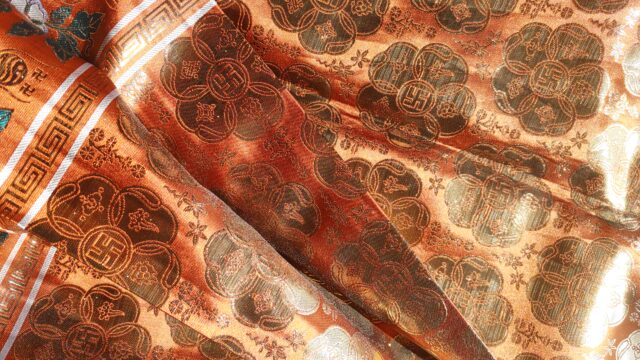「ぬぃの中国文学ノート」にご来訪ありがとうございます。
こちらの記事では、六朝後半のころの詩について解説してみたいとおもいます。もっとも、この時代は、詩以外のスタイルもまざっているような、独特の文体になっていたので、ちょっと話があちこち脱線します(笑)
ちなみに、六朝後期というと、わたしは梁~隋くらいまでだと思っています(中国では、隋も六朝にいれることが多いです)。ですが、実は唐のはじめ(初唐)も六朝らしい雰囲気がのこっているので、この記事では梁~初唐をみていきます。
あと、梁のひとつ前の南斉(なんせい)では、役人どうしの宴会などで送りあう“律詩っぽいもの(ひとつが八句)”だったり、長江あたりの民謡からうまれた五言絶句だったりが、文人たちのあいだでもつくられるようになりました。

というわけで、さっそく始めてみます。
梁
梁のときは、皇族たちのあいだで文学サロンがつくられました。そして、その中心にいた皇族たちがとても優美な作品をのこしました。
そんな中でも、皇太子だった蕭綱(しょうこう)は、とても繊細で技巧的な表現を得意にしています。
梅の花はいち早く春を知り、ある枝では陽をうけて金にかがやき、ある枝では雪を帯びて銀に光り、艶めきを四方の林に流して、華やぎを五方の路に延ばし、玉を垂らしてちいさく揺れて、氷の凝って雹をつけている。小さい葉のまだ出揃わず、枝は奥から出て古い幹に生え、高くあがって半ばに落ちて飛び、香りは風にのって遠くに流れて……
梅花特早、偏能識春。或承陽而發金、乍雑雪而被銀。吐艶四照之林、舒栄五衢之路。既玉綴而珠離、且冰懸而雹布。葉嫩出而未成、枝抽心而插故。摽半落而飛空、香随風而遠度。(蕭綱「梅花賦」より)
これが賦なんですよね……。漢代に流行った賦は、もっと擬態語がたくさんでてきて、しかも王宮や祭祀など大がかりなものを詠んでいましたが、こちらの作品は梅の花を詠んでいます(詩ではないですが、蕭綱の魅力がよく出ています)

特に好きなのは「ある枝は陽をあびて金に耀き、ある枝は雪を帯びて銀に濡れて(或承陽而發金、乍雑雪而被銀)」ですかね。こういう複雑できらびやかな細工もののような繊細さが蕭綱の作風です。
一方で、その弟の蕭繹(しょうえき)は、もうちょっと民謡っぽい作風を得意にしていました。
巫山の巫峡は長く、垂れる柳に垂れる楊。ひとつの心でともに折った枝をみて、あの人は故郷をなつかしむのでしょう。山は蓮の花に似てつややかに、流れは明月の光のように澄んで、寒い夜に猿の声がひびけば、あの方はきっと泣いているのでしょう。
巫山巫峡長、垂柳復垂楊。同心且同折、故人懐故郷。山似蓮花艶、流如明月光。寒夜猿声徹、游子泪沾裳。(蕭繹「折楊柳」)
こちらは、民間の旅する人のさびしさを詠んでいます。こういうふうに、南のほうの水の多い風景の中での恋愛がでてくるのが、六朝のころの民謡の特徴です。
「山は蓮の花のつやめきに似て……(山似蓮花艶)」の句が、自然の風物だけでできているのも民謡っぽくていいですよね。あと、同じ字をたくさんつかって、あえて素朴な雰囲気にするのも蕭繹らしさがあふれています。
というわけで、梁のころは中国南方の優美な自然をえがいた作品がたくさん生まれました。あと、ひとつ前の南斉とあわせて「斉梁」というと、耽美的な自然描写が多い――という雰囲気です。
陳
つづいては陳の作品です。陳の作品は、梁よりもさらに緑っぽい&シンプルになっている気がします。
きれいな木は春の洲にみちて、落ちた花は江に浮かんで、影は蓮花の石におちて、光は錦を濡らす流れにただよって、流れの色は桃色の水にうかんで、舞う香りは桂の舟に入る。そんなとき、別の潭(ふち)には仙菊があって、ひとりで秋の色を待っているのです。
奇樹満春洲、落蕊映江浮。影間蓮花石、光涵濯錦流。漾色随桃水、飄香入桂舟。別有仙潭菊、含芳独向秋。(張正見「賦得岸花臨水発詩」)
これは「岸花臨水発(岸の花は水にのぞんで咲く)」という句から想像してつくられた詩です(陳のころには、すでにある一句から連想してつくることが流行ります)。
さっきの蕭綱が緻密な工芸品のような感じだとしたら、こちらはより自然の風景をそのまま描いている気がしてきませんか。あと、陳のときの詩って、すごく光の色あいがきれいなんですよね。
石の瀬は浅くなったり深くなったりして、崖の霧も遠くで晴れたり曇ったりする中で、欠けた碑は古い路に横たわり、まがった木は荒れた道をふさいでいる。奥に入っては道もまだあり、歩きながら深く曲がっていく。高僧は遠いところにいて、深い山寺は心を休ませる。
石瀬乍深浅、崖煙遞有無。缺碑横古隧、盤木臥荒塗。行行備履歴、歩歩轔威紆。高僧迹共遠、勝地心相符。……(江総「入攝山棲霞寺詩」)
こちらも「石の瀬は浅くなったり深くなったり……(石瀬乍深浅)」が、水にあわせて色をかえる光がみえるようできれいです。そのあとの「欠けた碑は古い路に横たわる(缺碑横古隧)」も、「古(長らく整えられていない)」が薄暗くていいと思います。
こんな感じで、陳の詩はどこか植物などの陰翳がきれいなものが多いです。
隋
いよいよ隋に入りますが、じつは陳も隋もかなり短い王朝なので、両方の時代を生きている作者もいて、あまり大きく違いが分かれないという気がします。
さっきの陳のところでは、一つめのほうは八句で律詩のようなスタイルです(対句が3・4句め&5・6句めにあって、より律詩に近づいてます)。二つめのほうは、実はかなり長い古詩(古詩は長さのきまっていない詩です)なのですが、その途中をぬきだしたもので、すべて対句です。
こんな感じで、律詩らしい対句の整った詩ができてくる一方で、陳・隋あたりでは五言絶句や七言歌行などもたくさんでています。
夕方の江は動かずに、春の花はあふれるごとく開き、波は月のひかりに濡れて流れて、海のなみは星を浮かべたり。
暮江平不動、春花満正開。流波将月去、潮水帯星来。(隋・煬帝「春江花月夜 其一」
江南は遠くの閩甌(福建・浙江)までつづいていて、山東の英妙なひとはそちらまで行かれる。前には重なる障壁の山々をみて、その隣りには激しい流れの万里につづいていて、楓の葉が朝には京のほうに飛んでいって、手紙をいれた魚も長江のあたりを泳いでいるころでしょうか。
あなたは遠く茱萸(しゅゆ)の峰をこえて、私はいつでも明月の楼に住んでいるのですが、楼中では愁いがとける間もなく、また窓から春の景色をみているのです。鴛鴦(おしどり)は水草のあいだに遊び、鶴は鳴いて花もあざやかなときに、むなしく昔の枕をおいていた場所をながめれば、眉を書いてくれた人も長らく居ないのです。
江南地遠接閩甌、山東英妙屡経游。前瞻畳障千重阻、却帯驚湍万里流。楓葉朝飛向京洛、文魚夜過歴呉洲。君行遠度茱萸岭、妾住長依明月楼。楼中愁思不開嚬、始復臨窓望早春。鴛鴦水上萍初合、鳴鶴園中花并新。空憶常時角枕処、無復前日画眉人。……(薛道衡「豫章行」)
ひとつめが五言絶句、ふたつめが七言歌行です。五言絶句は、長江あたりの民謡からうまれてきたので、どちらかというとあでやかに湿った自然を詠むことが多いです。
七言歌行は、“七文字で歌行(漢代の民謡のこと。死生や離別などの生きていく中での悲しみを感じさせるものが多い)”ということなので、こちらもやはり民謡っぽさがあります。


こんなふうに、陳・隋の五言絶句&七言歌行は、民謡っぽさがすごく多めに入っているという感じです(梁のときにもこういう感じはあったけど、陳隋のほうがより民謡らしい)
ちなみに「陳隋」といったときは、濡れたような自然と民謡らしいなめらかな雰囲気――というニュアンスを感じます(六朝末期って、もっと完成されて技巧的かとおもったら、むしろシンプルになっていくのが意外でした)
初唐
というわけで、やっと初唐です。初唐っていうと、だいたい唐の建国~玄宗の即位くらいまでです(618~712年なので、かなり長い)
この時期は、初唐四傑といわれる王勃・楊炯・盧照鄰・駱賓王(おうぼつ・ようけい・ろしょうりん・らくひんおう)がすごく有名です。
この人たちの特徴は、賦の中に七言歌行と詩をまぜていることです。
春江はとろとろとして、春に会いたい人は来なくて、春の水に魚はあそんで、春の水辺に雁は飛び、春にあそぶ人に何処の景色がいいかと問えば、どんな年にも春はきて、どんな地にも春にあふれているのだけど。
そんなとき、遠くからきた人に出会えば、春に別れていく人もあり、春の景色は同じなのに、喜びと悲しみはそれぞれで、帰って春の山にて遊べば、春の草は遠く光って、わけもなく寂しい気がするのです。
春江澹容與、春期無処所。春水春魚楽、春汀春雁挙。……為問逐春人、年光幾処新。何年春不至、何地不宜春。亦有當春逢遠客、亦有當春別故人。風物雖同候、悲歓各異倫。帰去春山恣間放、蕙畹蘭皋行可望、何為悠悠坐惆悵。(王勃「春思賦」)
もはや賦とは思えないほどに五文字と七文字で埋め尽くされています。そして、内容も死生離別のかなしみの七言歌行っぽいですが、陳隋ふうのとろとろした自然の色味も入っています。対句の多さは、どこか律詩っぽくもありますね(そして、漢賦らしさはまるでなくなっている)
こんな感じで、初唐の人たちは、六朝後期の五言絶句や七言歌行、さらにはふつうの詩などを賦にまぜていきます。

というわけで、六朝後期~初唐についての詩を解説してみました。本来はかなり複雑な時期なので、もっといろいろあるかもですが、とりあえずの解説と思ってください(笑)お読みいただきありがとうございました。